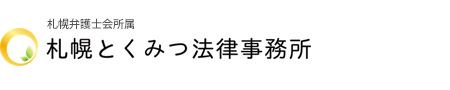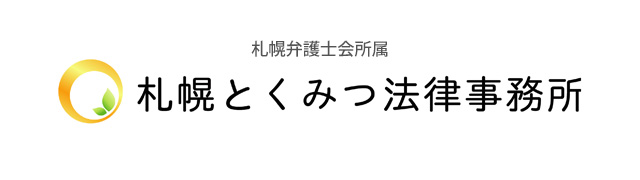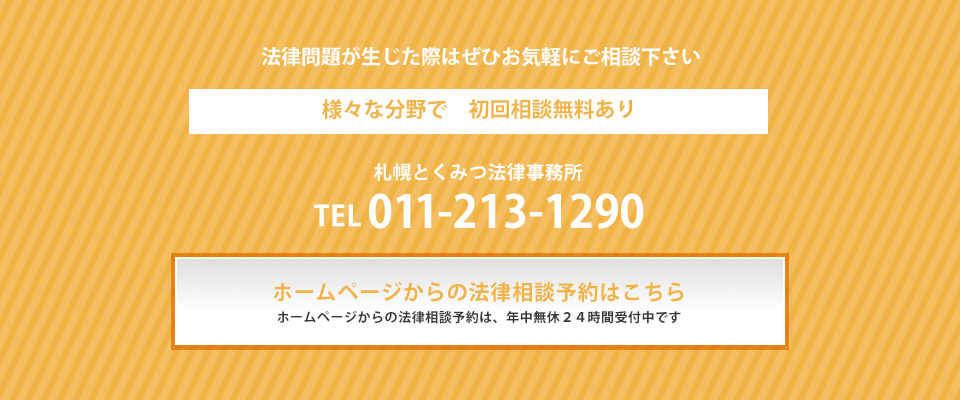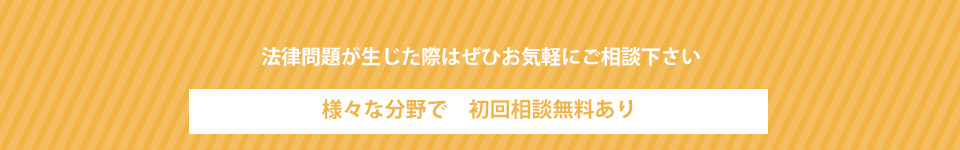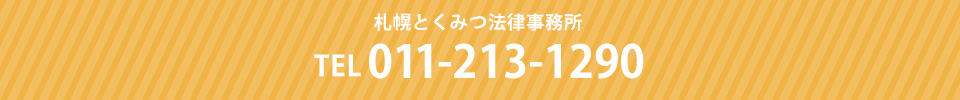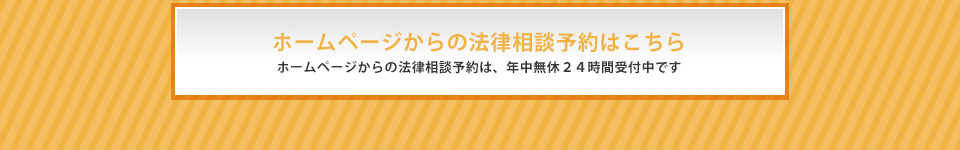協議離婚・調停離婚・裁判離婚の各手続
一口に「離婚する」と言っても、実は、離婚成立のための手続はいくつかあります。
代表的な離婚手続としては、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つがあります。
以下、それぞれの概要を簡単にご説明します。
① 協議離婚
協議離婚とは、夫婦が裁判所外で話し合いを行い、離婚についての協議を成立させる手続きです。
離婚全体のうち、ほとんどの場合がこの協議離婚によるものです。
未成年の子がいる場合は、親権者を決定しなければ離婚届を提出することはできませんが、逆に言うと親権者さえ決定すれば離婚届を提出することはできます。
もっとも、離婚の際に問題となるのは親権者の決定だけではありませんので、安易に協議離婚を成立させ、離婚届を提出するのは、場合によってはとても危険です。
② 調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所で夫婦が話し合いを行い、離婚についての話し合いがまとまった場合に成立する離婚手続です。
原則として、調停を申し立てられる側の住所地を管轄する家庭裁判所において調停手続を行うことになりますので、相手方が遠方に住んでいる場合には注意する必要があります。
調停では、夫婦が調停室へ交互に入り、2名の男女の調停委員に対して自分の考えや要望を伝えます。
③ 裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所での離婚訴訟によって成立する離婚手続です。
もっとも、原則としていきなり離婚訴訟を提起することはできません。
法律上、まずは離婚調停を申し立てて、調停手続での話し合いを行わなければならないことになっています。
これを調停前置主義といいます。
また、離婚訴訟が提起された場合においても、裁判上和解が成立し、これによって離婚成立となることもあります。
離婚訴訟が始まったからといって、必ずしも判決が下されるわけではないということです。
なお、離婚を認容する判決を得るには、民法770条1項各号の離婚理由が必要となります。