性格の不一致などの理由から相談者である夫が離婚を希望しているものの、妻は離婚に応じてくれないままであるため、別居に至ったというケースでした。
性格の不一致の他、離婚原因として決定的な事情は特にありませんでした。
当事者間では離婚の話が進まないため、弁護士により話を進めることとなりました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
性格の不一致などの理由から相談者である夫が離婚を希望しているものの、妻は離婚に応じてくれないままであるため、別居に至ったというケースでした。
性格の不一致の他、離婚原因として決定的な事情は特にありませんでした。
当事者間では離婚の話が進まないため、弁護士により話を進めることとなりました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
相談者は車を運転中、赤信号で停止していたところ、後続の車に後方から追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。
その後、整形外科への通院を続けていましたが、加害者側の保険会社から症状固定の打診がありました。
首の痛みや手のしびれなどがまだ残っており、対応に困った相談者は当事務所へ相談することにしました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
当事務所のゴールデンウィーク期間中の休業期間は、4月28日(土)〜5月6日(日)となっております。
ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、かねてより準備を進めておりました当事務所の新しいWebサイトを公開いたしました。
今後とも皆様へのサービス向上のため、改善・改修やコンテンツの充実に努めて参ります。

当事務所の弁護士徳満直亮が、メットライフ生命保険株式会社札幌代理店会様の定期総会において、オープンセミナーの講師を担当しました。
「民法大改正の概要」をテーマに、保険代理店の皆様にお話をさせて頂きました。
また、民法改正が保険実務にどのような影響を及ぼすのかという点について、私見も交えながら解説しました。
セミナー開催をご希望の企業様や事業主様は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
医療機関についての情報誌「メディカルページ 2017冬号 札幌版」に弁護士徳満直亮の記事が掲載されました。
札幌市内のセイコーマート全店で無料配布されておりますので、是非手に取ってみてご覧ください。
http://sapporo-medicalpage.net/about/bookinfo/
交通事故について、「人身事故に遭った後の治療と症状固定」というテーマで解説させて頂いております。
札幌地区で最も充実した医療情報ポータルサイト 「メディカルページ札幌」
当事務所の年末年始の休業期間は、平成29年12月27日(水)〜平成30年1月4日(木)となっております。
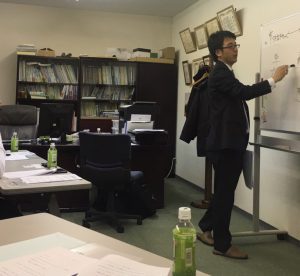
当事務所の弁護士徳満直亮が、以下の各セミナーについて講師を担当しました。
1 「家族信託 〜資産管理や相続についての新たな手法〜」 H29.11.27実施
大同生命保険株式会社函館営業所において、保険外交員様向けに、家族信託についてセミナー講師を務めさせて頂きました。
2 「民法大改正の概要について」 H29.11.27実施
北海道リスクマネジメント研究会の会員様向けに、民法改正の概要について、事例を交えながら解説させて頂きました。
3 「家族信託についての勉強会」 H29.12.5実施
保険代理店様向けの勉強会において講師を務めさせて頂き、成年後見制度などにも触れながら、家族信託を解説させて頂きました。
セミナー開催をご希望の企業様や事業主様は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
暴行・傷害事件を起こしてしまった場合、あるいは、家族や友人が暴行・傷害事件を起こしてしまった場合、どのようにその後対応すればよいのか、何も分からずパニックになるかもしれません。 何があっても暴力は許されることではありませんから、深く本人が反省すべきなのは当然のことですが、その後刑事手続などはどのように進むのでしょうか。弁護士の行う対応も踏まえ、ご説明したいと思います。
暴行罪については、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留(1日以上30日未満の刑事施設への拘置)若しくは科料(千円以上1万円未満)に処するという法定刑が定められており(刑法208条)、傷害罪については、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するという法定刑が定められております(刑法204条)。
暴力によって他人が生理機能に障害を負った場合には傷害罪となり、生理機能を損なわなかった場合には暴行罪となります。
生理機能の障害とは、平たく言うと怪我を負ったことなどですが、怪我だけでなく、病気の罹患なども含みます。
初犯の場合、罰金処分になることが多い印象ですが、特に傷害事件の場合、逮捕され、長期間の勾留が続くことも珍しくありません。
また、前科の有無や傷害結果の重大性などに応じ、公判請求がなされて刑事裁判が開かれ、懲役刑が求刑されることもあります。
他方、被害弁償や被害者との示談などの点が考慮され、早期釈放、不起訴処分となることもあります。
例えば、家族が暴行・傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合、今後の対応を考えるため、まずは本人に話を聞く必要があります。
ところが、逮捕期間(最大72時間)は、家族であっても、本人との面会を行うことはできません。
逮捕後、勾留手続きに移行した後は、家族も本人との面会を行うことはできますが、最大72時間の逮捕段階は、弁護士でなければ本人に会うことができないのです。
そこで、本人の言い分や、緊急に対応しなければならないことなどを確認するため、弁護人に依頼し、早急に本人に会いに行ってもらうことが望ましい対応と言えるでしょう。
本人の言い分を聞き、被疑事実に間違い無いということであれば、被害弁償や示談交渉を検討することになります。
この点は、前述のとおり、処分結果や釈放時期に大きな影響を与えます。
被害弁償や示談交渉については、被害者と連絡を取って行う必要がありますが、通常、加害者本人やその家族が行うことは困難ですので、弁護士に対応を依頼することになります。
また、処分結果には大きく影響しない可能性もありますが、被害弁償や示談交渉のほか、本人の反省や更生も当然ながら重要です。この点については、家族の監督など、周りの支えも必要となることが多いです。
以上の対応について、特に逮捕勾留されているケースではできる限り速やかに対応を開始する必要がありますが、在宅事件となった場合も、刑事処分が下されるまでの間に対応する必要がありますので、余裕をもって対応を開始すべきでしょう。
なお、逮捕勾留期間は最大合計23日間ですが、公判請求されて刑事裁判が開かれることとなった場合は、引き続き勾留が続くことになります。
当事務所は、捜査を受けている本人またはご家族からのご相談については、初回無料相談(30分)を実施しております。 (当事務所の営業時間は平日9時〜18時ですが、夜間や土日祝のご相談も承っております。その場合、30分5400円(税込)の相談料が発生しますが、相談の結果、正式にご依頼頂ければ相談料は無料となります。) 弁護士のスケジュール調整が可能であれば、当日にご相談に乗ることも可能です。 家族や知人が逮捕されている、在宅で捜査を受けているなどの場合、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
離婚問題について弁護士に相談する方は数多くいらっしゃいます。
しかし、いざ弁護士に離婚相談をしようと考えても、一体どういうタイミングで相談に行けばいいのか、よく分からないかもしれません。
以下、緊急度別に具体例を挙げながら、私の考える、弁護士のところへ離婚相談に行くべきタイミングをご説明します。
「緊急度低」とは書きましたが、実はこのタイミングでご相談頂くのがとても重要なケースもあります。
風邪は引き始めの対応が大事と言いますが、離婚問題も早めの対応が大切なケースが多々あります。
①離婚の話が進んでいるが、離婚条件に疑問がある場合
当事者間で離婚に向けての話が進んでいるものの、養育費や財産分与などの離婚条件について疑問がある場合、念のため弁護士に相談すると良いでしょう。
離婚条件の内容だけでなく、公正証書の形式とするなど、形式面についても併せてご相談されることをお勧めします。
一度正式に取り決めた離婚条件は、後からは覆すことができないおそれが大きいです。
内容が妥当ではなかった、漏れがあったなど、後から気づいてもあとの祭りとなってしまいかねません。
②これから離婚協議をしようと思うが、不安が大きい場合
これから離婚協議をしたいと考えるものの、配偶者の性格その他の事情などから揉める可能性が高い場合、予め弁護士に相談してもよいと思われます。
特に心配な点を弁護士に伝え、予め準備できることや対処すべきことについて確認しておくことをお勧めします。
すぐに弁護士に依頼する必要がなくとも、事前段階から継続的に弁護士に相談しておけば、いざという時にそのまま相談してきた弁護士に依頼できるので安心です。
③配偶者の不貞が発覚した場合
配偶者の不貞が発覚した場合、どのように対処すればいいのか混乱してしまうかもしれません。 そのような場合、弁護士に一度相談することをお勧めします。 すぐに行動には移さなくとも、弁護士に継続的に相談するのは有効です。
①当事者間では離婚の話が進まない場合
配偶者が感情的になってしまうなど、当事者間ではどうにも離婚協議が進まない場合、弁護士への相談をお勧めします。
弁護士が入ることにより、進展のなかった離婚協議や離婚調停がスムーズに進んだというケースは多くあります。
②配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求する場合
配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、自分自身で対応することも考えられますが、できれば弁護士へ一度相談することをお勧めします。
弁護士に依頼するのが困難な場合は、最低限、継続的に請求内容や請求方法などについて弁護士に相談するのがよいでしょう。
①配偶者に弁護士がついた場合
配偶者の代理人弁護士から通知が届くなど、配偶者に弁護士がついた場合、こちらもすぐに弁護士へ相談した方がよいでしょう。
弁護士を相手に交渉や調停を自分自身で行うことは、法的な面で不安になるだけでなく、精神的にも不安になってしまうことが多いです。
できればこちらも弁護士に相談の上、代理人となってもらうのがよいでしょう。
②弁護士や裁判所からの手紙が届いた場合
弁護士から慰謝料請求の通知書が届いた場合や、裁判所から調停の申立書などが届いた場合、当事者間だけでの話し合いを行うことはもはやできませんので、弁護士への相談を行った方がよいでしょう。
特に訴訟にまで発展した場合、自分自身で対応するのは非常にリスキーです。

当事務所では離婚問題を重点的に取り扱っております。
弁護士によっては、離婚問題をあまり取り扱わないという弁護士もいますが、当事務所では離婚問題を重点分野として積極的に取り扱っております。
離婚問題について経験豊富な弁護士がご相談に応じますので、安心してご相談ください。
当事務所では、離婚問題について、初回30分無料の法律相談を実施しております。 また、夜間や土日祝でのご相談も受け付けております(営業時間外での初回相談は、30分5000円(税別)の相談料が発生しますが、正式にご依頼いただいた場合、相談料は無料となります)。 お問い合わせフォームから24時間受け付けておりますので、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。