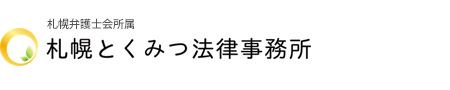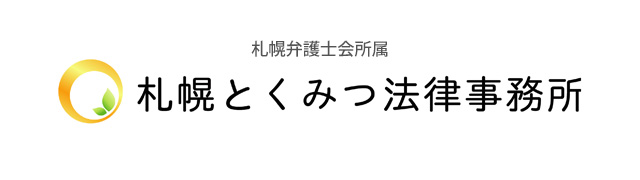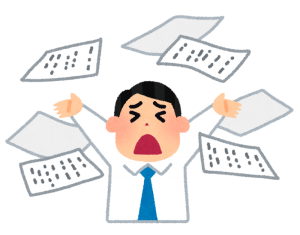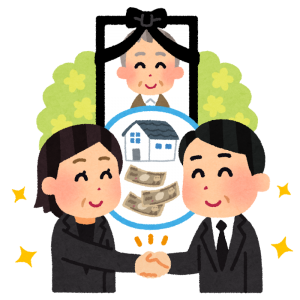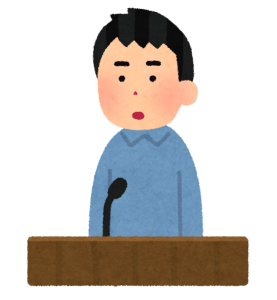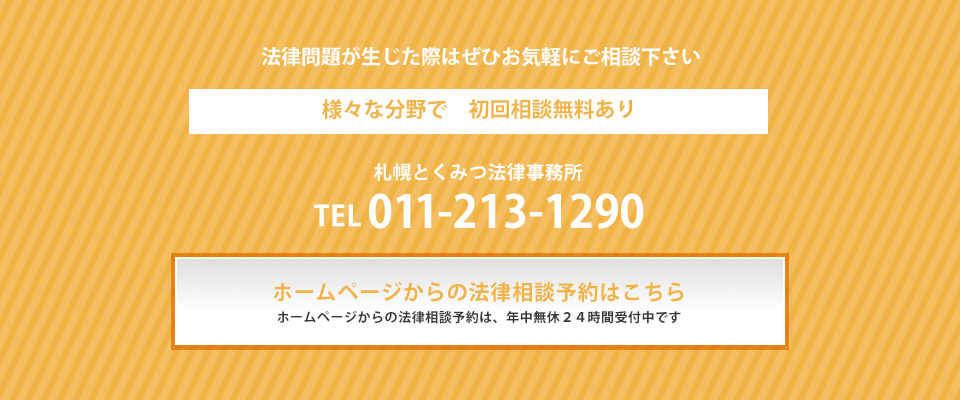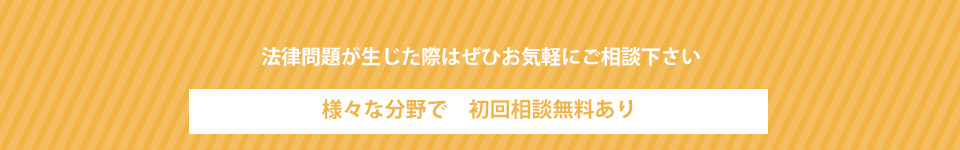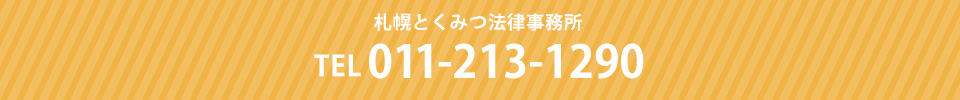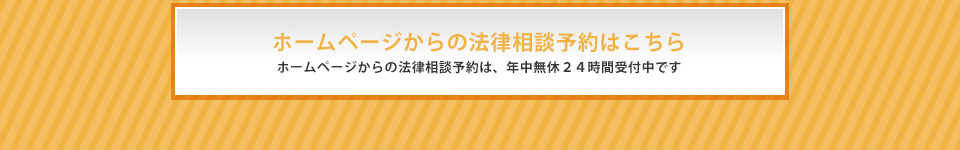完済できる見込みが確実でないのであれば債務整理を検討する
カードローンの返済や、クレジットカードのキャッシングやショッピングのリボ払いの支払いに困っていませんか。
また、最近ではアプリで借入のできるサービスもあり、より気軽に借金に手を出してしまう社会となっているかもしれませんが、気軽に借入をしてしまった場合にも高額の利息が生じる恐れがあります。
これらの返済が難しくなってしまった場合、どのように対応するべきでしょうか。
多くあるケースとして、「まだ返済していけるのではないか。」という甘い見込みを持ってしまうことです。
高額の利息や手数料の支払いもしなければならないにも関わらず、「何とかなるのではないか。」と考えてしまう方が多くいます。
そして、他のカード会社などから借り入れをして返済をすることで「何とか返済できている。」と錯覚してしまうことがあります。
しかしながら、他から借りて返済するという状況に陥った場合、高額の利息や手数料が雪だるま式にどんどん膨らむこととなり、いわゆる自転車操業状態に陥ってしまうのです。
したがって、自分自身の力で完済できる見込みが確実でないのであれば、速やかに債務整理を検討するのが最善の対応方法というべきでしょう。
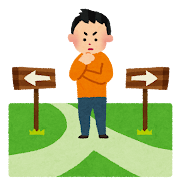
債務整理の相談は親族などではなく弁護士が対応すべき
債務整理とは、その名のとおり、借り入れなどの債務を整理して0にするための手続きのことをいいます。
それでは、どのようにして債務を整理するのがよいのでしょうか。
親族に相談し、親族に代わりに返済してもらうという対応をされる方がいます。
しかしながら、それでは相談者に代わって親族が負担を負ってしまうだけです。
また、親族に返済してもらった後、相談者が反省せずに再び借金を繰り返すということが往々にしてあります。
したがって、債務整理の相談は、親族などではなく専門家にするべきです。
そして、債務整理の方法は主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、これら全ての手続きに代理人となって対応することができるのは弁護士だけであるため、債務整理の相談相手として弁護士を選ぶことを強くお勧めします。
専門家である弁護士の話を聞いた上で、債務整理の手続きを選択することが重要となるのです。

経済的な再スタートを本気で考えることが重要
債務整理は、債務を整理して、経済的な更生に向けて人生の再スタートを切ることです。
当然のことながら、再スタートをした後、再び借入やクレジットカードに頼るようなことがあってはいけません。
また、債務整理の手続き自体も簡単なものではありません。
個人再生と自己破産については、これらの手続きを認めてもらうための準備や対応が必要となり、弁護士だけでなく相談者自身もこれらに対応しなければなりません。
任意整理についてはそもそも任意整理可能かどうかの判断が簡単ではない場合もあり、また、相談者自身も完済に向けての計画をしっかりと立てなければなりません。
したがって、「債務を整理して人生の再スタートを切り、2度と借入に頼らない。」ということを本気で決意し、債務整理の手続きにしっかりと対応することが必要になります。
このような決意をされている方については、当事務所の弁護士が全力でサポートさせて頂きますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。