相談者の両親は幼い頃に離婚し、相談者は父親と長年に渡って疎遠になっていました。
父親はその後再婚し、再婚相手との間にも1人の子がいました。
相談者は再婚相手の子を通じて父親が亡くなったことを知りました。
父親には不動産の他、数百万円の預貯金があるとのことでしたが、相談者は再婚相手側との遺産分割協議を自分でできる自信が無かったことから、弁護士に相談することにしました。
なお、父親は遺言書を書いていませんでした。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
相談者の両親は幼い頃に離婚し、相談者は父親と長年に渡って疎遠になっていました。
父親はその後再婚し、再婚相手との間にも1人の子がいました。
相談者は再婚相手の子を通じて父親が亡くなったことを知りました。
父親には不動産の他、数百万円の預貯金があるとのことでしたが、相談者は再婚相手側との遺産分割協議を自分でできる自信が無かったことから、弁護士に相談することにしました。
なお、父親は遺言書を書いていませんでした。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

「自己破産」という言葉を聞いたことのある方は多いと思います。
もっとも、そもそも自己破産とは何か、自己破産をするとどうなるのか、どんな手続きなのかについて、答えることのできる方は少ないのではないでしょうか。
自己破産とは、簡単に言うと、借金の返済が困難な状況に陥ったときに、裁判所に申し立てて、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
もちろんどのような場合にも全額免除してもらえるわけではなく、例えば、返済に充てることのできる一定の財産がある場合は、その財産を配当(返済)に充てた上で、残りの返済義務を免除してもらうという流れになります。
また、自己破産は裁判所へ申し立てて行う手続きですが、破産法や破産手続きに関する専門知識が必要となるため、弁護士に依頼するのが通常です。
弁護士に事実関係の説明や必要資料の提出を行い、弁護士に代理人となってもらい、裁判所へ申し立てるという流れになります。
なお、自己破産について代理人となることができるのは弁護士だけです。
すなわち、弁護士でなければ、本人に代わって債権者とのやりとりをすることや、自己破産申立て後、裁判官との面談がある場合などに同席することはできません。

自己破産の手続きが無事に通った場合、前述のとおり、借金返済の義務が免除されます。これを「免責」と言います。
破産する人にとって、この免責が最大のメリットといえます。
それでは、自己破産をするとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
「破産したら人生が終わる。」などと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
自己破産は、経済的な更生をするための手続きであり、借金返済がどうにも立ち行かなくなってしまった方が人生を再スタートするための制度です。
「自己破産だけはなんとしてでも避けたい。」と考えるあまりに弁護士へ相談することなどを遅らせてしまうと、むしろ借金は膨れ上がることになり、危険です。
自己破産にはデメリットには以下のようなものがありますが、実際上は、その人にとってあまり不利益にならないということも多いです。
①一定の財産は配当のために処分される可能性がある
相当額の財産を持っている場合、これが処分されて借金返済のために充てられる可能性があります。
しかし、「自己破産をすると家具も家電も全て持っていかれてしまう。」などというわけでは全くありません。
「自由財産」という生活に必要な財産については自己破産をしても保持できるとされています。
実際には、自由財産を超える財産を持っているというケースの方がむしろ少ない印象です。
②一定期間、資格や職業の制限が生じる
破産手続きを行なっている期間中、資格や職業が制限されることがあります。
制限の対象となるのは、他人のお金を管理するような仕事であり、具体的には、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、旅行業務取扱管理者、証券外務員、宅地建物取引士、建築士事務所開設者など、様々な資格や職業が対象になります。
しかしながら、破産手続きをしたからといって、このような仕事を一生できないというわけではありません。
破産手続きは通常、免責許可の決定が確定することで終結しますが、その後に「復権」という形で制限が無くなります。
したがって、破産手続きの開始決定から終結まではおおよそ4か月程度であるため、通常はこの期間の間だけ、資格や職業が制限されるということになります。
③官報により公告がなされる
自己破産を申し立てた後、自己破産手続きをしていることが「官報」という国の発行する機関紙に掲載されます。
しかしながら、官報を隅々までチェックしているという人は通常いませんので、官報を通じて自己破産のことを知人などに知られるということはまずありません。
ただし、自己破産により制限を受ける職業などの場合に、勤務先や関係者が官報を定期的にチェックするということはあるようです。
なお、自己破産の場合だけでなく、個人再生を申し立てた場合も、官報に掲載されることになります。
④数年程度、ローンやクレジットカードを利用できなくなる
自己破産をした場合、信用情報に「事故」として記録が載るため、数年程度、ローンを組むことやクレジットカードを作ることができなくなります。いわゆる「ブラックリスト」というものです。
しかしながら、自己破産の場合に限らず、後述の個人再生や任意整理という債務整理の方法でもブラックリストには載ります。
また、債務整理をしないまま、返済を滞納した状態を続ければ、結局のところブラックリストに載ることになります。
そもそも自己破産などによる債務整理は、経済的更生を果たし、人生を再スタートさせるということに目的があります。
再スタートしたにもかかわらず、再びすぐに借り入れに頼るということはあってはいけません。
したがって、借り入れを一定期間できないということは、むしろ人生を再スタートさせた人にとって良いことであると、前向きに捉えるべきでしょう。
なお、どの程度時間が経てば借り入れの審査が通るのかという点は、審査をする業者によって様々であるため、比較的早期に審査が通ったということもあるようです。

債務整理には、自己破産の他に、個人再生、任意整理という方法もあります。
個人再生は、自己破産と同じように裁判所に対して申し立てる手続きです。
自己破産では原則として借金全額を免除されるのに対し、個人再生では借金の一部を免除してもらった上で、残りを返済していく手続きになります。
任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所に申し立てる手続きではありません。
貸金業者などの債権者との和解交渉を弁護士に任せる手続きです。
任意整理は、和解後の利息をカットしてもらうという点に大きな意義があります。
もっとも、任意整理では原則として現在の借金額を減らせるわけではないため、任意整理をしたとしても返済に無理がないかどうか、慎重に検討する必要があります。
どの方法を用いるべきかについては、必ず専門家である弁護士と相談して決めるべきでしょう。
一人で悩み続けるのではなく、まずは弁護士に相談することから検討しましょう。
| 当事務所の夏季休業期間は、8月8日(土)〜8月10日(月)、8月13日(木)〜8月16日(日)となっております。 |
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。

盗撮や痴漢などの迷惑行為は、各都道府県の条例によって取り締まられています。
北海道では、北海道迷惑行為防止条例という条例があり、公共の場所等での盗撮や痴漢などの卑わいな行為をした者について、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
「公共の場所」と記載しましたが、住居、浴場、トイレなどの場所にいる、一部でも衣服を着けていない人を盗撮する行為についても、同様に罰則の対象とされています。
また、常習としてこれらの行為をした者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
※令和2年5月時点の条例内容です。
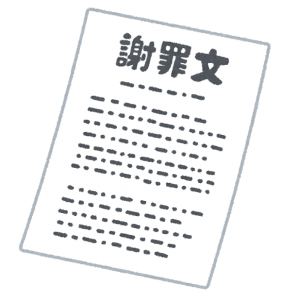
盗撮や痴漢のような被害者のいる犯罪の場合、被害者への謝罪や慰謝料(示談金)の支払いを考える必要があることは言うまでもありません。
被害者のいる犯罪の場合、通常、被害者との示談が刑事罰の判断において最も重視されます。
それでは、示談を検討するタイミングはいつ頃なのでしょうか。
盗撮や痴漢などの迷惑行為について警察から捜査を受ける場合、逮捕や勾留がなされる場合と、身体拘束がされずに在宅のまま捜査がなされる場合があります。
前者の場合、捜査のための身体拘束の期間は最大23日間と決められています。
他方、後者の在宅捜査の場合、このような期間制限は無いため、警察からしばらく連絡が来ないなど、捜査に一定の時間がかかる場合があります。
しかしながら、在宅捜査の場合にも、被害者への謝罪や示談を行うことのできる時間が無限にあるわけではありません。
したがって、謝罪や示談については、在宅捜査の場合であっても早期段階から速やかに検討するべきといえるでしょう。

被害者への謝罪や示談交渉のことを検討するとしても、通常、加害者本人が被害者と直接接触することはできません。
仮に接触可能な状況にあるとしても、加害者が自分で被害者側と交渉し、示談の交渉や手続きを行うのは危険です。
そこで、代わりに謝罪や示談交渉の対応してくれる者を探す必要がありますが、加害者の弁護人となってこれらの対応をできる資格者は弁護士だけです。
加害者の弁護人になった弁護士は、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察の担当者とのやりとりにも対応し、弁護活動を行います。
したがって、被害者への謝罪や示談交渉を検討する場合は、まずは弁護士へ相談することから始めるべきでしょう。

当事務所では、法律相談や打ち合わせで弁護士が面談を行う際、新型コロナウイルスの感染防止のため、以下の各対策を実施しております。
・弁護士やスタッフのマスク着用
・弁護士との間にアクリル板の設置
・窓を開けることによる換気
・各面談が終了するごとに相談室の消毒
・スタッフの健康管理の徹底

交通事故に遭って怪我を負った場合、損害賠償をしっかりと対応してもらえるかどうかは、加害者側の自動車保険への加入状況がまずは重要になります。
自動車保険には、法律で加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険では足りない部分を補う任意保険の2種類があります。
加害者が自賠責保険に加入しているものの、任意保険には加入していない場合、自賠責保険で受けられる賠償の金額は「自賠責基準」と呼ばれる低い基準で算定された金額になります。
加害者が自賠責保険にすら加入していない場合も、政府保障事業という制度を活用し、自賠責基準の補償を受けることは可能です。
加害者が任意保険に加入している場合には、通常、任意保険会社の担当者が被害者への対応を行います。
そして、任意保険は自賠責保険では足りない部分を補う保険であることから、自賠責基準を上回る損害賠償を期待することができます。
もっとも、後述のとおり、加害者が任意保険に加入しているからといって、納得のいく損害賠償をしてもらえるとは限りません。

交通事故で負った怪我が重傷の場合、治療を続けても後遺症が残ってしまう可能性があります。
例えば、骨折や脱臼の怪我を負った場合、以前よりも足が曲がらない、腕を上げられないなど、可動域が制限されてしまう後遺症が残ることがあります。
後遺症が認められるかどうか、認められるとしてもどのような後遺症が認定されるかによって、慰謝料などの損害賠償金の金額は大きく変わってきます。
したがって、後遺症が残る場合、適正な後遺症の認定を得ることが重要となります。

怪我が重傷である場合、慰謝料などの損害額も大きなものになります。
したがって、加害者側にはしっかりと損害賠償に応じてもらう必要がありますが、前述の任意保険に加入している場合であっても、いわゆる「任意保険基準」の損害賠償金が提示されることが通常です。
「任意保険基準」とは、任意保険会社独自の基準であり、裁判において基準とされる「裁判基準」の損害賠償金よりも低い基準です。
最も高額の「裁判基準」による損害賠償をしてもらうためには、被害者が弁護士を立てる必要があります。
弁護士が「裁判基準」による示談交渉を行うことにより、「任意保険基準」の倍額以上の損害賠償金額になることも珍しくありません。
また、適正な後遺症を認定してもらうために、弁護士のサポートが重要になることもあります。
交通事故で負った怪我が重傷であるほど、弁護士を立てるか否かによって生じる損害賠償金の差額は大きくなるのです。
したがって、交通事故で負った怪我が重傷の場合、弁護士の活用を必ず検討するべきといえます。
当事務所のゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されておりますが、当事務所では、パソコンやスマートフォンで利用可能な「Zoom」を用いたオンライン相談(テレビ電話の形式)も実施しております。
オンライン相談のご利用もぜひご検討ください。
相談者は札幌在住の60代の男性であり、道東に実家のある方でした。
父親は15年以上前に亡くなっており、相談者の母親は実家で一人暮らしをしていましたが、その母親も6年前に亡くなりました。
相談者は3人兄弟の次男でしたが、実家の近くに住んでいた長男夫婦が母親の身の回りの世話をしていたため、実家も長男夫婦が引き継ぐということになりました。
もっとも、具体的な遺産分割の手続きはなされていませんでした。
具体的な手続きはありませんでしたが、長男の家系が全てを引き継ぐということが昔からの慣習であったため、相談者としては長男である兄が実家も含めた相続財産全てを管理しているものと考えていました。
ところが、最近になって、実家の固定資産税に関する納付依頼の通知が相談者の元に届きました。
兄が相続財産を引き継いでいると認識していた相談者は驚き、弁護士に相談することにしました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
当事務所では、法律相談については面談での実施を原則としておりますが、当事務所へお越し頂くことが困難なケースも多いのではないかと思います。
そこで、ビデオ会議システム「Zoom」によるオンライン相談を開始することとしました。
「Zoom」はパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでも簡単に利用することのできるツールであり、実際に対面しているかのようなやりとりが可能になります。
ご来所が難しい方は、当事務所の弁護士へのオンライン相談をぜひご検討ください。
オンライン(Zoom)相談をご希望の場合、ご利用の流れは以下のとおりになります。
①ビデオ会議システム「Zoom」ご利用の準備。
パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでもご利用可能です。
(パソコン等の端末にスピーカー、マイクの機能が備わっていない場合、それぞれ別途ご準備いただく必要があります。)
↓
②電話、問い合わせフォーム、LINEのいずれかからオンライン相談の予約。
氏名、電話番号、メールアドレス、住所、簡単なご相談概要の他、ご相談日時の希望を第3希望程度までお知らせください。
↓
③予約したご相談日時になりましたら、当事務所の弁護士からZoomミーティングへ招待するURLを、メールでお送りします。
↓
④招待URLをクリックして進めていくと、Zoomミーティングが始まりますので、オンライン相談を開始します。
※相談開始時に、免許証などの身分証明書により、氏名や住所のご本人確認をさせて頂きますので、お手元に身分証明書をご準備ください。
※オンライン相談実施の様子を録音録画することは禁止させて頂いております。
※通信環境はご相談者様自身で整えて頂く必要があります。
↓
⑤相談料が発生した場合、請求書をメールでお送りします。お支払方法は銀行振込になります。
事件処理をご依頼の場合、ご依頼に必要となる委任契約書の取り交わし等を郵送で対応させて頂きます。
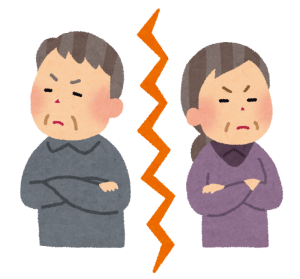
「離婚したい」と本格的に考えた時、子どものことやお金のこと、自宅や仕事のことなど、様々なことが頭に思い浮かぶと思います。
いずれも離婚後の生活にとって大事な事柄ですが、相手との離婚協議で特に何が問題になるかをまず整理する必要があります。
つまり、相手と揉めることが予想される点をまずは整理すると良いでしょう。
子どものことであれば、親権がどちらになるのか、親権者ではなくなる親の子どもとの面会交流はどうするのか、養育費はどうするのかなどです。
お金のことであれば、財産分与はどうするのか、年金分割の必要はあるのか、慰謝料請求の可能性はあるかなどです。
また、別居後、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)も重要な問題です。
クレジットカードの家族カードを作っているというケースも多くありますが、これをどうするかという問題もあります。
財産分与については、自宅をどうするのか、まだ残っている住宅ローンをどうするのか、自宅が夫婦共有名義になっている場合はどうするのかなど、自宅の問題にも派生します。
将来発生が予測される退職金も財産分与の対象となる可能性があるため、この点も検討事項になります。
そして、そもそも相手が離婚に応じるかどうかという点も検討しておく必要があります。相手が離婚に応じてくれない場合にどう対処するかということも考えておかなければなりません。
このような様々な検討事項のうち、相手との離婚協議でどれが問題になるのかということをまず整理する必要があるのです。

離婚協議を進める中で、お金のことを全く考えなくて良いというケースはまず無いでしょう。
したがって、ほとんどのケースで、夫婦の収入や財産を把握しておくことが重要になります。
「お金のことは妻に全て任せているので分からない。」「夫の収入はよく知らない。」とおっしゃるご相談者はよくいらっしゃいますが、可能であれば、離婚協議や別居を始める前に、夫婦の収入や財産のことを把握しておくことが望ましいといえます。

離婚協議で問題になることをまず整理する必要があるとご説明しましたが、離婚の手続きだけを見ると、互いに離婚届を書いて役所へ提出すれば、離婚は成立します。
そして、子どもがいる場合も、親権者をどちらにするかという指定さえあれば離婚届を提出することはできます。
しかしながら、お金のことや自宅のことなどを取り決めないまま衝動的に離婚届を書くことは大きなリスクを伴う恐れがあり、避けるべきでしょう。
例えば、離婚が成立すれば、夫婦ではなくなるため、婚姻費用を請求することができなくなります。
また、財産分与について言えば、法的には離婚後も2年以内であれば請求可能なのですが、離婚前と離婚後であれば交渉の仕方が変わってきます。
すなわち、離婚した後では、離婚する前に比べて財産分与や慰謝料などの交渉が難しくなるケースがしばしばあるのです。
以上のように、衝動的に離婚届を書いてしまうことにはリスクを伴うおそれがありますので、一度思いとどまって慎重に検討することが重要です。