5月6日(金)は、勝手ながら休業させて頂きます。
その他のゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。
5月6日(金)は、勝手ながら休業させて頂きます。
その他のゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。
相談者は50代であり、仕事帰りに車で信号待ちの停車をしていたところ、後方から大型車に衝突される交通事故に遭いました。
車は大きく損傷し、相談者も外傷性頚椎椎間板ヘルニアなどの怪我を負いました。
そして、画像上、椎間板突出による脊髄への圧迫が認められることなどから、後遺障害等級12級13号の後遺症が認定されました。
ところが、加害者側の保険会社からは、椎間板ヘルニアについては交通事故との因果関係が乏しいなどと主張がなされ、最も低額な自賠責基準での損害賠償金しか提示されませんでした。
そこで、相談者は当事務所の弁護士へ相談することにしました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

離婚の相談の際、「相手に慰謝料を請求したい。」という要望を伺うことがあります。
芸能人の離婚報道などで高額な慰謝料の支払いを聞くことがあるため、離婚に伴って慰謝料の清算が必要と考える方が多いのかもしれません。
もっとも、慰謝料は離婚に伴って必ず発生するというものではありません。
確かに、主に一方の配偶者にのみ離婚の原因がある場合には、離婚を余儀なくされたことを理由に慰謝料が発生する可能性があります。
しかしながら、離婚の原因が配偶者の一方だけでなく双方にあるというケースも多いため、慰謝料が特段生じないということも多くあります。
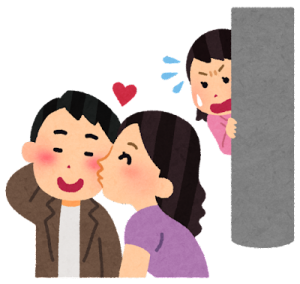
それでは、離婚に伴って慰謝料が生じることの多いケースにはどのようなものがあるでしょうか。
典型的なケースとしては、不倫や肉体的な暴力が挙げられます。
不倫については、不倫をした配偶者だけでなく、不倫相手に対して慰謝料を請求することも考えられるため、この点も踏まえて方針を検討する必要があります。
モラハラについての相談を受けることもありますが、一言にモラハラと言っても、その内容や程度、経緯はケースバイケースであるため、これらの事実関係をよく検討する必要があります。

慰謝料は、精神的苦痛を被った人を慰謝するためのお金です。
それでは、慰謝料の金額についてはどのようにして算定されるでしょうか。
例えば、不倫についてはおおよそ200万円程度が基準になることが多いように思われますが、当然のことながら、事案によって金額は様々であり、それぞれのケースに応じて判断されることになります。
婚姻期間や不倫の態様・期間、不倫後の婚姻関係など、複数の事情を総合的に考慮した上で、具体的な慰謝料の金額を算定することになります。
慰謝料問題については金額のみならず、請求方法や手続、証拠関係などについても検討する必要があるため、まずは弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
当事務所の年末年始休業期間は、12月28日(火)〜1月3日(月)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
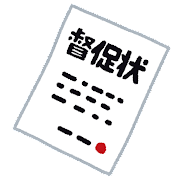
カードローンやクレジットカードの支払いを滞納してしまい、そのまま何年も放置状態になっているということは無いでしょうか。
貸金業者からも連絡が来なくなったと思っていたところ、何年も経った後に債権回収業者などから手紙が届くということがあります。
このような場合、何年も滞納していたことに対する多額の遅延損害金が加算されて請求されていることが多いため、膨れ上がった金額に驚くでしょう。
何年も昔の借金について、絶対に支払わなければならないのでしょうか?
いいえ、時効による消滅を主張できる可能性があるのです。
特に、最後に返済をした時から5年を経過している場合、時効を主張できる可能性が高いといえますので、注意する必要があります。
もっとも、例えば、改正民法が施行された2020年4月よりも前に、業者からではなく個人から借り入れていた借金の場合には、5年ではなく10年の消滅時効期間が適用される可能性があるなど、別の判断基準が適用される場合もあります。
したがって、最終返済日から5年を経過しているかどうかだけで全て判別できるわけではありませんが、これが消滅時効に関する一つの指標にはなります。

借金が時効で消滅している可能性が高い場合、注意しなければならないことがあります。
それは、督促の手紙を送ってきた債権回収業者などへ安易に連絡をしたり、返済をしたりしないことです。
なぜならば、これらの行為が時効の更新にあたるとして、債権者側から消滅時効の成立を争われる事態になりかねないからです。
「時効の更新」とは、平たく言えば、時効期間がリセットされてしまうことです。
つまり、「時効の更新」に該当すると、すでに何年も経過していた時効期間が0にリセットされてしまうのです。
したがって、安易に業者へ連絡をしたり、返済をしたりする前に、まずは債務整理に詳しい弁護士へ相談することを強くお勧めします。
業者側に対して時効を主張することを「時効の援用」と言いますが、自分自身で対応することには大きな不安を感じる方が多いと思われますので、そのような場合にはまずは弁護士へご相談ください。
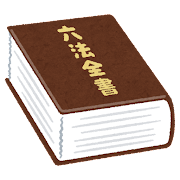
これまで時効に関する話をしてきましたが、時効のことだけを考えれば良いというわけでは全くありません。
例えば、1社のカードローンについては時効による消滅を主張できるものの、他にも多額の借り入れがある場合、当然のことながら、他の借り入れのことも含めた全体としての債務整理を考えなければなりません。
また、時効だろうと考えていたところ、実は時効が完成していないことが判明した場合、他の方法による債務整理を考えなければなりません。
例えば、滞納していた借金について実は業者から訴訟を起こされていて、その判決が確定している場合、前述の「時効の更新」に該当し、時効が完成していないということがあります。
以上のとおり、ただ単に時効のことだけを考えれば良いのではなく、いくつかの債務整理の方法を念頭に置いた上で、最善の選択を検討しなければなりません。
当事務所では、消滅時効の援用手続きを対応させて頂けるのはもちろんのこと、任意整理・自己破産・個人再生という全ての債務整理の方法を踏まえた上で、弁護士が相談に乗らせて頂きます。
まずはお気軽に当事務所までお問い合わせの上、ご相談ください。
当事務所の夏季休業期間は、8月7日(土)〜8月10日(火)、8月12日(木)〜8月15日(日)となっております。また、8月11日については16時までの営業時間となります。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
当事務所のゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。

大企業では、法的問題に関する対応は法務部や顧問弁護士が行うということが一般的であると思われます。
しかし、日本の中小企業では、法務部という部署がそもそも存在しない場合がほとんどです。
中小企業においては、総務部や役員、あるいは社長自身が法的問題に対応するということが多いのではないでしょうか。
企業の経営を全体的に管理する者が、法的問題への対応についても兼任するということが多く、専門的な部署が設置されていることは少ないといえます。
このように、中小企業で法的問題への対応がいわば「後回し」になっているのは、以下のような理由からではないでしょうか。
①売上アップなど、会社にとって法務よりも重要なことが多くある。
②そもそも法的問題が起きることがあまり無い。
③法的問題が生じることもあるが、専門部署を作るほど多くはない。

このように、中小企業においては法務があまり重視されていない現状があります。
しかしながら、法的問題の対応を後回しにすることにより、法的リスクが顕在化し、会社が大きな不利益を被る恐れがあります。
また、問題が顕在化していなくとも、契約書や利用規約の作成、従業員の労務管理など、法律を踏まえて対応しなければならない業務は数多くあります。
そこで、中小企業がこれらの対応を専門家に任せるために、弁護士と顧問契約を締結することが考えられます。
弁護士との顧問契約とは、一定の顧問料を弁護士に定期的に支払うことにより、弁護士に会社の顧問となってもらうことをいいます。
法律の専門家である顧問弁護士に法的問題の対応を任せることにより、会社は安心して事業に集中することができます。
また、会社の顧問弁護士の存在を対外的に示すことにより、取引先などからの信頼を得られる他、会社に対して不当な行為を企むような相手方に対しては一種の牽制効果も期待できます。
そして、法務部などの専門部署を新たに作ることに比べれば、コストは格段に小さくなります。
法務部の立ち上げに比べればコストは小さいと述べましたが、顧問契約に伴って生じる顧問料も法律事務所や弁護士により様々です。
例えば、毎月10万円を超える顧問料を支払っているものの、法律相談や法的問題はほとんど生じていないということであれば、顧問弁護士の必要性に疑問を感じてしまうかもしれません。
そこで、札幌とくみつ法律事務所では、各企業のご希望に応じた柔軟な顧問料プランをご用意しています。
「弁護士に会社の顧問となってもらいたいが、法的対応を依頼することはほとんど無いと思う。」ということであれば、月額1万1000円(税込)の顧問料プランをお勧めしております。
他方で、「法律相談や契約作成など、法律問題に関連する業務が数多くある。」ということであれば、月額5万5000円(税込)の顧問料プランをお勧めします。月額の顧問料は高くなりますが、顧問弁護士に法的対応を依頼する際には、無料で対応できる範囲が広くなり、別途費用が生じる場合も割引率が大きくなります。
このように、当事務所では、各企業様のご希望に応じて顧問契約のプランを提案させて頂いております。
顧問契約に関するご相談は相談料無料で対応しておりますので、まずはお気軽に当事務所の弁護士へご相談ください。
当事務所の年末年始休業期間は、12月28日(月)〜1月3日(日)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
相談者は、認知症で施設に入所した叔母の財産管理のことで困っていました。
叔母には夫も子もいなかったため、相談者がやむを得ず面倒を見ていました。
特に困っていたのは、叔母が一人で暮らしていた自宅のことでした。
叔母が施設に入所した後、空き家になったため、建物の状態が悪くなる一方でした。
また、築年数のかなり古い建物であったため、近隣に被害を及ぼすような事故が起きないか、相談者は不安に思っていました。
預貯金や生命保険の管理についても負担を感じていたことから、弁護士に相談することにしました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。