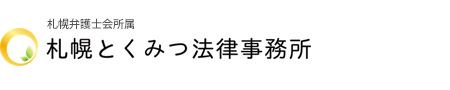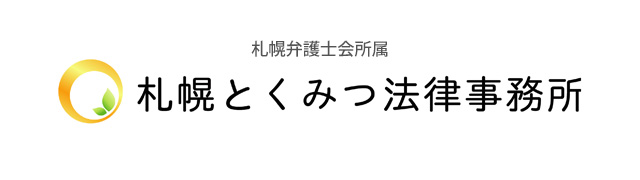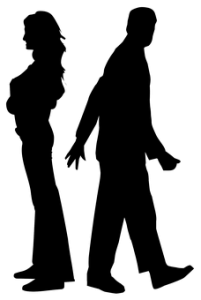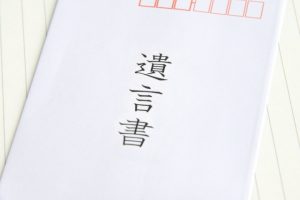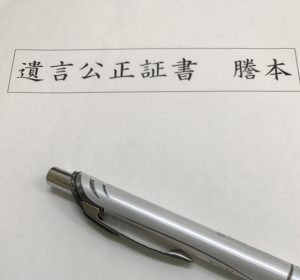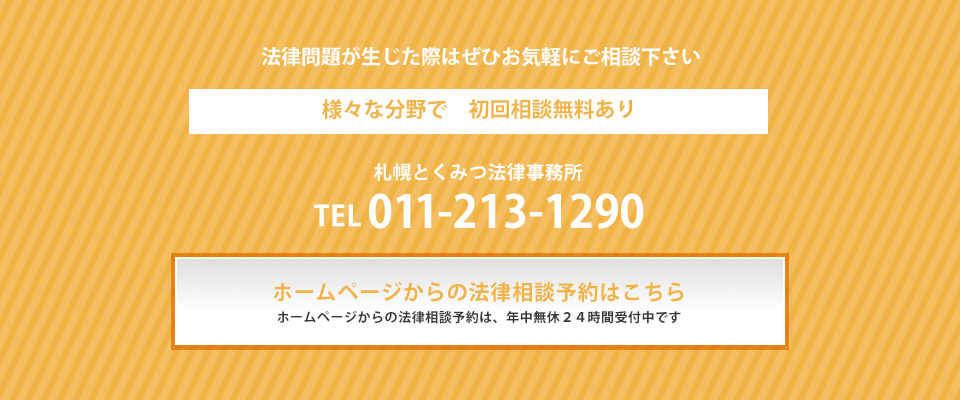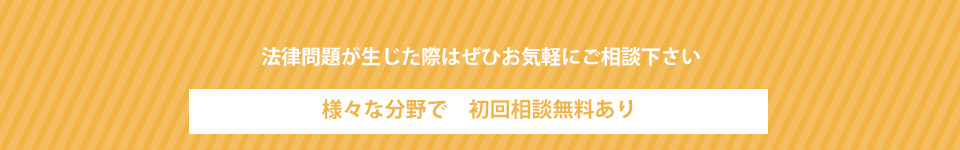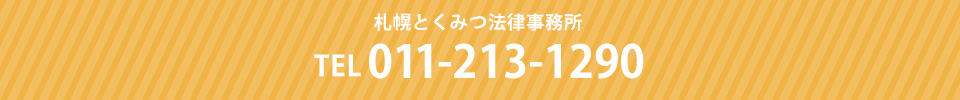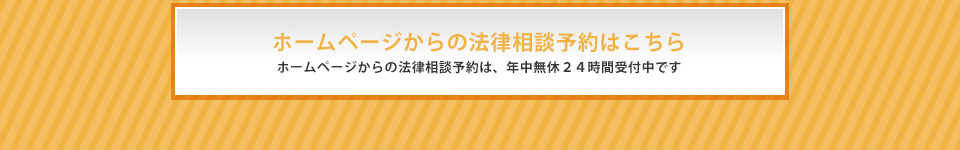債務整理とは
カードローンやクレジットカードのリボ払い、住宅ローンなどの借金のことで悩んでいる方は、数多くいらっしゃいます。
多重債務の状態になると、「何とか借金を返済しないと。」という悩みが常に頭から離れなくなります。
そのような方に検討頂きたいのが、債務整理です。
日本では、借金がどうしても返せなくなってしまった方のために、人生の再スタートを切ることのできる制度が用意されています。
これが債務整理と呼ばれるものです。
債務整理には大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産という3つの手続きがあります。
「自己破産」と聞くと、人生の終わりのようなイメージがあるかもしれません。
しかし、自己破産などの債務整理は、むしろ新しい人生を始めるための制度であり、経済的に更生するための手段です。
自分にとって適切な手続きを利用し、債務整理を行えば、借金の返済に追われる生活とは決別し、新たな人生をスタートさせることができるのです。

借金や債務整理のことを誰に相談すればよい?
債務整理という言葉を知っても、自分にとってどのような債務整理が適切なのか、具体的にどのような手続きをとればいいのか、全く分からないというのが普通です。
それでは、誰に相談すればよいでしょうか。
債務整理は、破産法や民事再生法などの法律に基づいて行う手続きですので、親族や知人などではなく、法律の専門家である弁護士に相談するべきです。
自分であれこれ考えている間にも負債は膨らんでしまいます。
借金問題を解決に導くため、債務整理のことを熟知する弁護士に相談されることを強くお勧めします。

「自転車操業状態」に陥っているのであればすぐに法律相談を
弁護士に相談しようと考えても、法律事務所に問い合わせるのはなかなか敷居が高く感じてしまうかもしれません。
また、どういうタイミングで法律相談に行けばいいのか、悩むと思います。
一つの基準としては、返済をするためにまた借金をするという、いわゆる「自転車操業状態」に陥ってしまっている場合は、すぐに弁護士に相談すべきといえるでしょう。
このような状態に陥っている場合、返済の目処が立つどころか、雪だるま式に借金が膨らんでいく恐れが大きいため、速やかに債務整理を検討するべきです。
自転車操業状態に陥っているにも関わらず、借り入れのできる限度額に達すれば、また別のところから借り入れをするなどして、負債を膨らませ続けることはとても危険です。
ついには返済をできなくなって滞納し、借金だけでなく家賃や税金も滞納し、さらには訴訟を起こされ、給与を差し押さえられるなどの事態に陥れば、債務整理において選べる手段はどんどん狭まってしまいます。
借金の問題を解決し、人生の再スタートを切るために、弁護士には是非とも早期の段階でご相談ください。